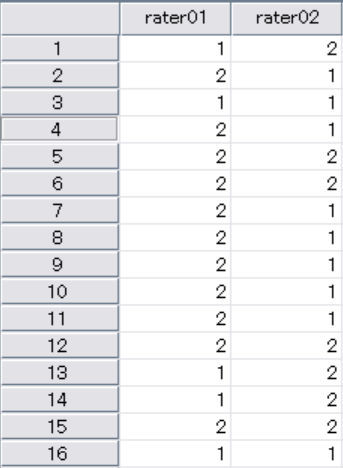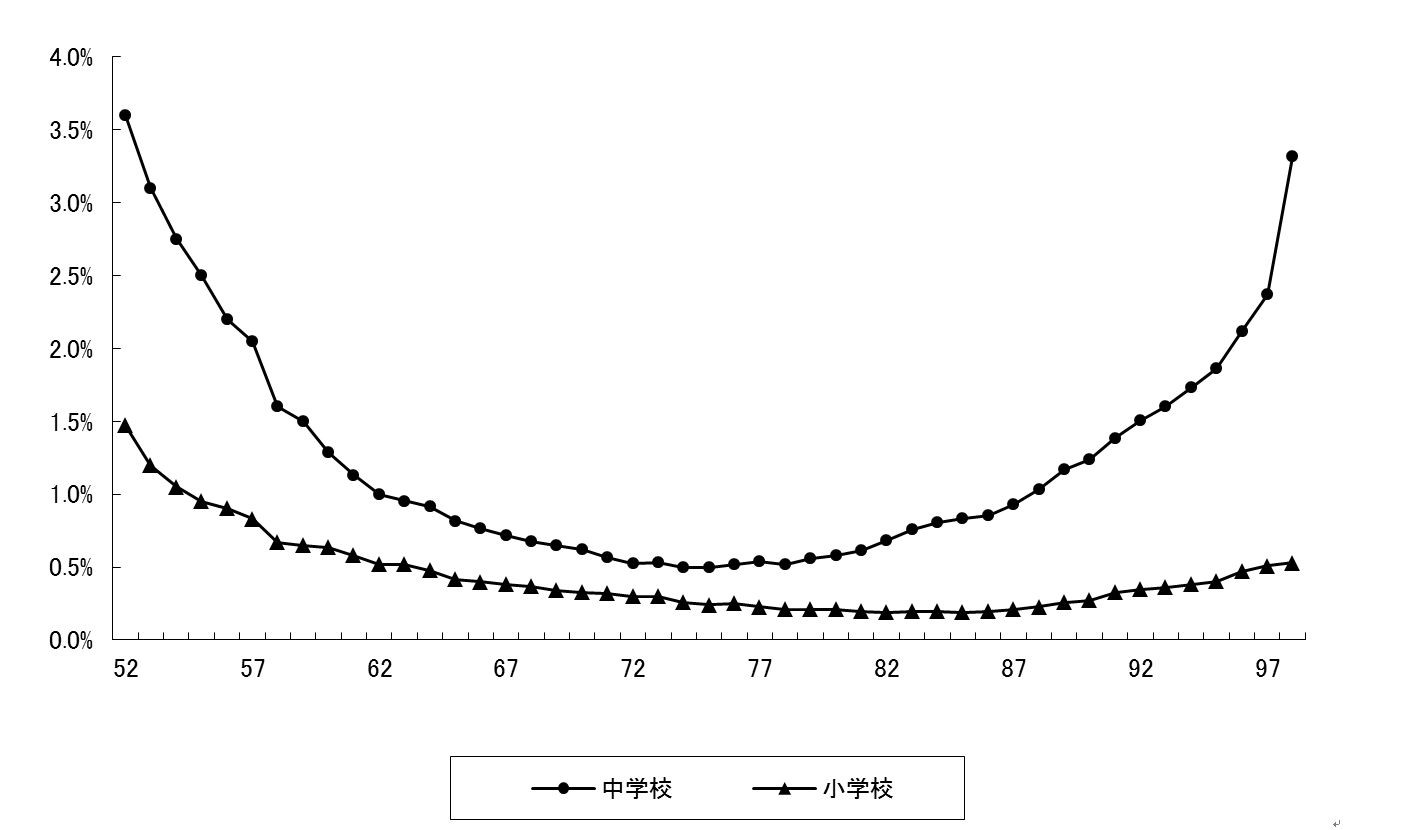Mplusの説明書に掲載されている例7.7から。
https://www.statmodel.com/usersguide/chapter7.shtml
潜在クラス分析に使用する変数が順序づけられていないカテゴリカル変数である例。
パスダイアグラムは以下のように書く。潜在クラス数が複数あってもCは一つだけである。

TITLE: This is an example of a LCA with unordered categorical latent class indicators using automatic starting values with random starts DATA: FILE IS ex7.7.dat; VARIABLE: NAMES ARE u1-u4; CLASSES = c (2); NOMINAL = u1-u4; ANALYSIS: TYPE = MIXTURE; OUTPUT: TECH11 TECH14;
CLASSES
クラス数の指定のオプション。ここでは2クラスでの計算を指定している。
NOMINAL
名目変数として扱う変数を指定する。
カテゴリカル変数の場合にはCATEGORICALと指定する。この分析(順序づけられていないカテゴリカル変数)なのでNOMINALが指定されているが、CATEGORICALと書いても分析結果は基本的には変わらない。実際に走らせてみると、クラス1とクラス2が入れ替わったが、それ以外の出力は同じ。
ただし、CATEGORICALと書かないと反応確率が出力されない。
ANALYSIS
デフォルトの標準誤差はロバスト推定が使われている。いわゆるロバスト最尤推定法(MLR)である。他の推定法を使用する際には、ESTIMATORオプションを追加する。例えば、ベイズ推定の場合には"ESTIMATOR = BAYES;"を追加する。といっても、MLR以外の推定法として指定できるのは最尤法(ML)とベイズ推定法(BAYES)のみである。ロバスト重み付き最小二乗法(WLSMV)などの最小二乗法系の推定法は使用できない。潜在クラス分析は最尤推定法で行うので当たり前といえば当たり前である。
各オプションは下記の4つ。
ランダム初期値: STARTS = 200 10(デフォルトは10 2)
初期最適化の反復回数: STITERATION = 50(デフォルトは10)
ブートストラップの反復回数: LRBBOOTSTRAP = 50;
ブートストラップの尤度比検定の初期値: LRTSTARTS = 0 0 100 20;
OUTPUT
デフォルトに含まれていない出力を指定するコマンド。
Mplusの例ではTECH1とTECH8が指定されているが、ここではTECH11とTECH14を指定している。
TECH11はVuong-Lo-Mendell-Rubin LIikelihood Ratio Test (VLMR) の出力、TECH14はBootstrapped Likelihood Ratio Test (BLRT)の出力ができる。これらの統計量はクラス数が妥当か否かを判断する際には必要となる。どちらか一つ選ぶのであればBLRTなので、TECH14をだけいれることが多いかもしれない。
TECH14によって指定したクラス数より一つ少ないカイ二乗値の差と検定が出力される。P値が低い場合(例えば5%水準以下)であれば、クラス数の増加によってモデルが最適化されていると判断する。下記の出力結果をみると、クラス数を2に指定して、P値は0.000であるので、一つクラスを増やして、CLASSES = c (3);として再分析してみた方がよいかもしれない。TECH14を指定するとブートストラップを施行するので計算時間が割と長くなる。
ちなみに、TECH8オプションはモデルの最適化の履歴が出力されるほか、分析中に所要時間がわかる。ただ、出力が長くなり、使わない部分が増えるので不要かもしれない。
出力
Information Criteria Akaike (AIC) 42850.964 Bayesian (BIC) 42961.756 Sample-Size Adjusted BIC 42907.736 (n* = (n + 2) / 24) FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES Latent Classes 1 3713.04544 0.74261 2 1286.95456 0.25739 CLASSIFICATION QUALITY Entropy 0.343 TECHNICAL 11 OUTPUT VUONG-LO-MENDELL-RUBIN LIKELIHOOD RATIO TEST FOR 1 (H0) VERSUS 2 CLASSES H0 Loglikelihood Value -21445.523 2 Times the Loglikelihood Difference 74.083 Difference in the Number of Parameters 9 Mean 14.753 Standard Deviation 9.570 P-Value 0.0008 LO-MENDELL-RUBIN ADJUSTED LRT TEST Value 73.129 P-Value 0.0008 TECHNICAL 14 OUTPUT PARAMETRIC BOOTSTRAPPED LIKELIHOOD RATIO TEST FOR 1 (H0) VERSUS 2 CLASSES H0 Loglikelihood Value -21445.523 2 Times the Loglikelihood Difference 74.083 Difference in the Number of Parameters 9 Approximate P-Value 0.0000 Successful Bootstrap Draws 10