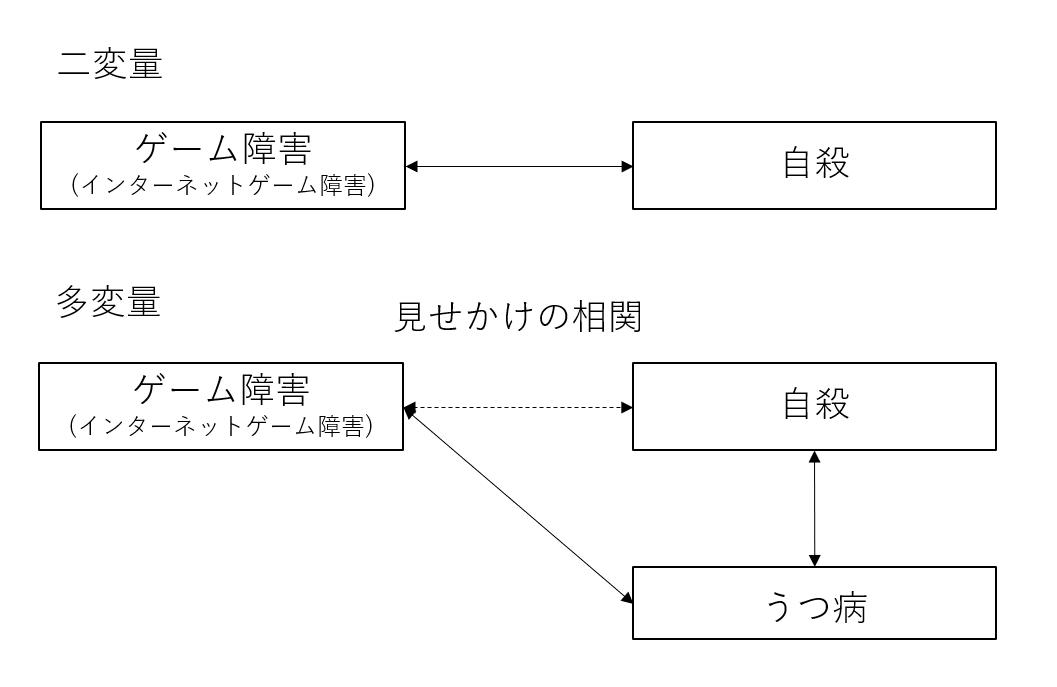前回からの続き
- Kearney, Christopher A. 2008. “An Interdisciplinary Model of School Absenteeism in Youth to Inform Professional Practice and Public Policy.” Educational Psychology Review 20 (3): 257–82.
専門家の実践への影響
提案されたアブセンティーズムのモデルは、個々のケースに対する専門家の実践にいくつかの示唆を与えている。最初の包括的な評価方法には、(1)欠席を問題のないものと問題のあるものに分類すること、(2)現在および過去の欠席の頻度、種類、機能を決定すること、(3)子どもの欠席の原因となる近位および遠位の主要な要因を多軸的に評価することが含まれる。問題のある欠席をしている青少年を臨床的に評価するための推奨事項は、複数の情報源から入手可能である(Beidel and Turner 2005; Heyne et al. 2004; Heyne and Rollings 2002; Kearney 2003; Kearney et al. 2005)。
提案された問題のあるアブセンティーズムのモデルでは、様々なリスクと重症度のレベルで介入を推奨することも可能である(表4)。一次的な欠席のレベルでは、親、家族、学校が協力的であるにもかかわらず、適切な登校ができない精神病質を持つ青少年がいる。そのため、効果的な臨床的介入は、症状を軽減し、子供を通常の授業に復帰させるために考案されている。マニュアルを含むいくつかの出版物には、これらの手順が詳しく説明されている(Heyne et al.2002; Heyne and Rollings 2002; Kearney 2007b; Kearney and Albano 2007a, b; Kearney and Silverman 1999; King et al.)
しかし、先に述べたように、問題のある欠席をする青少年に対応する臨床家や教育者は、この行動に影響を与える他の多くの近位および遠位の要因を認識しなければならない。二次的なレベルでは、精神病理を持つ青少年は、子どもの欠席に適切に対応することが困難な親と交わっている。そのような困難は、離反、学校関係者への好戦的な態度、混乱、親による学校閉鎖、親による精神病などの形で現れる可能性がある。このような場合には、臨床家は子どもに対する心理的な処置を補うために、欠席を解決するために親の積極的な参加を促す戦略をとる必要がある(Heyne et al. 2002; Kearney et al.2007). この二次的なレベルでの問題となる欠席は、夫婦間や家族間の機能不全を伴うこともあり、これに対処しなければならない(McShane et al. 2001; Table 4)。
三次レベルでは、青少年の精神病理や親・家族の機能障害が、仲間や限られた学校からの影響など、より広い文脈の変数と交差する(DeWit et al.2000). よくある例は、非行に走るきっかけを作るような逸脱した仲間と付き合っている子供である。継続的な欠席は、親や学校が関与しないこと、学校外で目に見える報酬を求める傾向が強くなること、学校ベースの課外活動との連携がうまくいかないことによって促進される可能性がある。学校側の不関与は、過重な負担を強いられる職員が出席率を十分に監視せず、早退した生徒を放置するという形で現れる(Fallis and Opotow 2003)。第3段階の介入には、初期のパートタイムプログラムや代替出席プログラム、および表4のその他の戦略を追求するために、学校関係者との緊密な連携が必要である。
第4段階では、子ども、親、家族、仲間の影響が、学校風土の悪化など学校を基盤とした広範な問題と交錯する。特定の学校や地区で欠席率が高い理由は前述したが、特に重要なのは、留年が多いこと、生徒の学業上のニーズへの対応が不十分であること、柔軟性に欠ける懲戒行為、教師の欠席などである(Brookmeyer et al.2006; Jimerson et al.2002; Lee and Burkham 2003)。個人的にも家族的にも深刻な問題を抱えている若者は、このような特徴を持つ学校では、社会的にも学問的にも強力なサポートを得られない可能性があり、その結果、学校をドロップアウトする可能性が高くなる。また、臨床医や保護者は、個々の生徒の欠席問題に対応できないような厳しい官僚制度を乗り越えることに困難を感じるかもしれない(Bimler and Kirkland 2001)。第4次レベルでの臨床的介入は、表4の他の戦略に加えて、子どもの安全と教育上のニーズが本当に満たされているかどうかを精査する必要がある(Astor et al. 2005; Hernandez and Seem 2004; Vreeman and Carroll 2007)。
一般的なレベルでは、図1の影響力のある要因の多くは、問題のある欠席率の個々のケースに関係しているものである。このレベルでは、深刻な地域社会の要因が他の要因と相まって、特定の地域や学校で広範な欠席率を生み出している。このような生徒の多くは、メンタルヘルスサービスを受けることができず、臨床家がこのようなケースを目にすることはほとんどありません。一般的に問題のある欠席に対しては、マルチシステミック・セラピー(Thomas 2006)のような研究に基づいた幅広いプログラムを用いて臨床介入を行う。マルチシステミック・セラピーは、個人、家族、仲間、学校、地域社会などの複数のレベルで反社会的行動に対処するために、家庭と地域社会を基盤とした集中的な介入を行うものである(Brown et al.1999)。この介入は、学校の成績と出席率の改善に効果的である(Barth et al.2007; Henggeler et al.1999)。
問題のある欠席をしている青少年に対する臨床的介入は進化し続けており、多くの場合、子どもだけでなく、親、家族、仲間、学校、地域社会に関連する緊急事態に対処するために拡大しなければならない。長期的には、問題のある欠席のすべてのケースに対する最も効果的な臨床的介入の形は、不登校に関連する主要な公共および学校関連の政策や介入と交差しなければならないであろう。次のセクションでは、これらの広範な変数を、学校ベースの人員配置のための推奨事項とともに議論する。
表4 問題のある学校欠席者に対する介入レベルの提案
介入のレベル
一次レベル(子ども中心の欠席率)
不安、抑うつ、その他の関連する症状を軽減するための臨床技術
徐々に通常の教室に復帰させる。
出席と欠席に対する罰則
治療者と学校関係者の定期的な連携により、進捗状況を確認し、登校の新たな障害を解決する。
担任教師の役割を再構築し、リスクのある生徒を特定する。
登校拒否の兆候について学校関係者を教育する。
保護者と学校関係者の協力体制を強化し、拡大する欠席のケースに直ちに対応する。
二次レベル(子供+親+家族を重視した欠席率) プライマリーレベルの戦略
保護者と学校関係者の間の相違を調整する
保護者が介入することの重要性を教育する
子供の登校に関する親の不安を解消する
夫婦間の機能不全、家族間の対立やコミュニケーションの問題、一貫性のない監督や規律の実践、家族のストレス要因を軽減するための臨床技術と適切な紹介
欠席した子どもに連絡を取り、登校を再開させるためのピア・メンターの活用。
必要に応じて、子供のために学校の欠席率調査チームに働きかける。
逃亡の危険性がある時は、子供の監視を強化する
不適切な行動に対する教室内での非公式な対応
紛争の解決
三次レベル(子供+親+家族+仲間を中心とした欠席率) 一次・二次レベルの戦略
セラピストと学校関係者が協力して、代替プログラムやパートタイムの出席プログラムを追求し、毎日の出席を監視し、すぐに対処できる計画を立てる。
毎日の出席状況を監視し、早退に直ちに対処する計画を立て、新たな欠席について保護者に定期的にフィードバックする。
健康、精神衛生、家族、財務、法律、早期教育などのサービスを、学校を拠点とした一つの環境に集約することで、偏見や移動の負担を軽減し、サービスの連携を強化する。
個別の教育計画(504プラン)を作成し、授業のスケジュール、補習の蓄積、成績や単位に関する期待値を修正する。
担任と最初のクラスの間で生徒のピアグループを維持する。
四次レベル(子ども+親+家族+仲間+学校側の欠席) 第1、第2、第3段階の戦略
子どもの安全と教育上のニーズに対応しているかどうかを調べる
教師、クラス、学校の変更が可能か、より刺激的なクラスや教師との連携が可能か
学校の不備、融通の利かなさ、危険性、対応の悪さに関する子どもの訴えが本当に正当なものかどうかを検討する。
学校への出席がある程度達成されるまで、少年司法制度への紹介を遅らせる。
社会的、学業的問題を抱え、特別教育の必要性が満たされていない青少年に対し、カリキュラムや指導を修正、カスタマイズし、指導者を提供する。
出席を認め、報いるための学校ベースのインセンティブプログラムを設計する。
生徒と生徒、生徒と教師の間の対立を解決する。
親と子のサポートグループの調整
慢性的な欠席の問題を抱える青少年のために、独立した教育ユニットを設置する。
若者が新しくて大きな施設に適応できるよう、サマーブリッジなどの移行プログラムを開発する。
システム全体での暴力の削減
学校教員の多様性を高め、学区内の民族的に多様な家族とのコミュニケーションを増やす
第4レベル(子ども+親+家族+仲間+学校+地域密着型の欠席率) 第1次と第2次、第3次と第4次の戦略
マルチシステミック・セラピーなど、研究に基づいた幅広い介入方法
学校を拠点とするチームを、警察、裁判所、ソーシャルサービス、教会、地域組織など、多様な青少年に対応する外部リソースと連携させる。
慢性的な欠席率を持つ生徒のために、警察による一斉捜索や学校内での特別な管理ユニットの設置
学校内に欠席裁判や不登校裁判を設置する。
罰則付きの学習環境でも出席を必要とする法的措置。罰則の例としては、居残り、学校内での停学、学校を拠点とした社会奉仕活動などがあり、通常の教室環境への移行が容易になる。
Pertinent references: Barnet et al. 2004; Broussard 2003; DeSocio et al. 2007; Epstein and Sheldon 2002; Fantuzzo et al. 2005; Garrison 2006; Gibson and Bejinez 2002; Heyne and Rollings 2002; Jones 2004; Kearney 2008b; Kearney and Albano 2007a; Kearney et al. 2001; Lehr et al. 2003; Lever et al. 2004; McCluskey et al. 2004; Mueller and Stoddard 2006; Oros et al. 2000; Portwood et al. 2005; Reid 2006, 2007; Reynolds et al. 2001; Richtman 2007; Shoenfelt and Huddleston 2006; Sinclair et al. 2005; Southwell 2006; Teasley 2004; White et al. 2001.
公共政策への影響
概念化や介入と同様に、一般的な青少年の学校欠席率に関する公共政策は、個々の分野や教育地区によって比較的分断されている。義務教育法や欠席防止法の制定を促す公共政策の中心は、おそらく公序良俗政策であろう。公序良俗政策とは一般的に、社会の混乱や不安を軽減するために法律や犯罪防止戦略を実施することを指す。例えば、義務教育法はもともとヨーロッパやアメリカで、都市化、工業化、移民などの急激な変化に直面して、教育を受けた労働力や社会秩序の必要性に応えて制定された(Kearney 2001; Mangan 1994; Paterson 1989; Zhang 2004)。最近では、多くの公共秩序政策が、不登校などの低レベルの違反や身分上の違法行為にも集中している(Hornqvist 2004)。 不登校防止法はいくつかの地域で制定されており、青少年の不登校に対して親に罰金を科したり、生活保護費を連動させたりしている。
欠席した場合に親に罰金を科したり、生活保護費を青少年の出席率に連動させたり、長期欠席の場合に青少年の運転免許を剥奪したり、欠席者に対して法的措置を取るためのゼロ・トレランスなどを奨励する反立法がいくつかの管轄区域で成立している(Ethridge and Percy 1993; James and Freeze 2006; Southwell 2006; Washington State Institute for Public Policy 1996; Zimmerman and Fishman 2001)。さらに、多くの管轄区域では、欠席に対する司法的対応に基づいて学区に資金を提供している(Reid 2003)。2001 年に「the No Child Left Behind Act 」が成立し、「適切な年間進度」の「その他の指標」の 1 つと して、公立中学校の生徒の卒業率が挙げられるようになると、このような慣行が加速する可能性がある(US Department of Education 2007)。また、不登校などの身分犯に対する公共政策の変化により、地域に根ざした治療などの脱施設的な介入が増えている(Steinhart 1996)。しかし、一般的には、多くの地域や学校では、犯罪主義的な欠席モデルが採用されている(Bazemore et al.2004; Pell 2000)。
欠席率に関する一連の政策がバラバラであったり、公序良俗に反する政策のみに頼ったりすることの特に不利な点は、出席率に問題のある青少年の実質的な異質性や複雑性が無視されたり、軽視されたりすることである。例えば、学校に通えないような心理的問題を抱えている青少年の多くは、学校関係者からの紹介で警察の一斉捜索や少年院に収容されている。また、治安の悪い学校、規則を重んじる学校、勉強嫌いの学校が原因で不登校になっている少年は、ギャング関連の活動をしている非行少年と同じように扱われている。また、不登校予防に関する文献では、個人的な要因、家族的な要因、学校や地域社会の要因に基づいて青少年を区別しようとする試みはほとんどなされていない。
この論文で紹介されている学際的なモデルは、公共政策に重要な影響を与える。このモデルは、公序良俗やゼロトレランス政策のようなグローバルで画一的なアプローチではなく、問題のある欠席を組織的に対処するためのより微妙な方法を採用している。実際、学校や欠席防止プログラムの中で、様々なタイプの若者を特定し、適切な介入を行うトリアージ戦略を求めている著者もいる(Kearney 2008b; Kearney and Bates 2005; Reid 2007)。トリアージ戦略に基づいた問題のあるアブセンティーズムについての学区の方針は、専門的な実践と同様に、様々なレベルでの介入を伴うものである。これらのレベルは、欠席の重症度と頻度だけでなく、重症度、頻度、影響を与える要因の種類にも依存するであろう。また、これらのレベルでは、学校関係者の数、時間、外部機関への相談などの資源の配分も異なってくる。ここでは、表4に関連した例示的なレベルについて説明する。
一次レベルでは、欠席問題の芽生え、軽度の症状、文脈上のリスク要因が少ないケースに対して、一人の学校関係者が良性の対策を実施することができる。典型的な例としては、小学校から中学校への移行が困難な子どもたち、初めて学校関連の苦痛を感じた子どもたち、あるいは軽度の破壊的行動で帰宅を余儀なくされた子どもたちが挙げられる。これらのケースでは、学習面、家庭面、その他の問題はほとんど見られません。このような場合の学校での介入は、表4のようなものが考えられる。
第二次レベルでは、欠席率が悪化した生徒や、背景にある危険因子を持つ生徒に対して、学校関係者の小規模で非公式なチームがより実質的な対策を実施することができる。典型的な例としては、保護者に内緒で授業をサボった生徒、より強い適応障害を持つ生徒、違法欠席の閾値や前述の「問題のある欠席」の定義の基準3に近づいている生徒などが挙げられる。これらのケースに対応する学校関係者の少人数チームには、主治医、ガイダンスカウンセラー、ピアメンターなどが考えられる(Pritchard and Williams 2001; Reid 2003)。このような中等教育レベルでの学校ベースの介入には、ピア・メンターや表4のその他の戦略を用いることができる。
第三次レベルでは、正式な学校をベースにしたチームが、法的な閾値や前述の問題のあるアブセンティーズムの定義の基準3を超える重度の問題のある欠席を追跡し、対処することができる。典型的な例としては、定期的に学校を欠席したり、いくつかのクラスで落第点を取ったり、学校内での不品行を伴って学校に出席することに強い苦痛を感じている青少年が挙げられる。正式な学校ベースのチームには、主要な管理者(校長、学部長)、指導カウンセラー、学校心理士、教師、および必要に応じて一般の人々が参加することができる。この第三次レベルでの学校ベースの主な介入方法としては、外部のメンタルヘルスなどの専門家との定期的な相談や、表4のその他の戦略が考えられる。
第四次レベルでは、学校をベースにしたチームを設立し、欠席率を下げるために学校をベースにした変化の有用性を調査することが考えられる。このチームは、カリキュラムや指導方法をカスタマイズしたり、表4のその他の戦略を追求する責任を負うことができる。一般的なレベルでは、これらの正式な学校ベースのチームは、非常に高いシステムレベルの問題となる欠席率に対処するために、多くの外部リソースと連携しなければならない(表4)。
この記事で紹介した学際的モデルは、学校の欠席率に関する州や連邦政府の政策にも影響を与える可能性がある。学校への資金援助は、欠席の程度、代替教育プログラムの革新的な開発、様々なタイプの欠席をしている青少年や欠席の原因となっている学校関連の要因を区別して評価し対処するトリアージ戦略の使用などを含む計算式に基づいて一部行われる可能性がある。さらに、学際的な研究チームに助成金を提供し、問題のある欠席にさまざまなレベルで対処することの有用性を調査することもできる。最後に、保護者や教師、その他の人々に、欠席の潜在的な危険性や、特定の地域で問題に対処するために利用可能なリソースについて教育するための公共教育プログラムを実施することができる。これらの取り組みの補助的で重要な目標は、一般人や専門家が分野を超えて努力を重ね、知識を共有し、青少年の問題となる欠席に関する出版物の比較可能性をさらに高めることである。
最終コメント
本論文の主な目的は、研究者、実務者、政策立案者の間でコンセンサスを得るための学際的なモデルを提供することである。この分野の専門家は、努力を調整し、知識を共有し、発表された文献間の比較可能性を高めるために、分野を超えて協力してこのモデルを検証し、修正することが強く推奨される。この目的のために、専門家は、子ども、親、家族、仲間、学校、地域社会の要因を十分に考慮したインタビューやアンケートなどの共通の評価方法を開発しなければならない。また、専門家は、問題のある欠席やその関連する危険因子に対処するための助成金申請や実践的な戦略を策定するために協力しなければならない。そのためには、多面的なアプローチが必要であり、個人レベル、システムレベルで欠席を予防、削減するための効率的な方法を導き出すことが必要である。